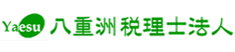いま、国内のお産に関わる医療は分かれ目にたっています。
全国的に少子化に伴う経営難や医師不足によって出産施設が減少し、産科機能の一定の集約化によって自治体ごとのお産の受入体制に変化が起きています。
NHKでは医療計画を策定する都道府県に対し出産施設の状況を調査しました。
令和6年9月から10月にかけての調査の結果、全国1,700あまりある市町村のうち、出産施設が1つもない自治体は1,042市町村と、全体の6割近くにのぼることが分かりました。
こうした分べん空白市町村の広がりは、少子化によって産科機能の集約化を図らなければならないなど、やむを得ない地域も多くあると言われています。
とは言え、病院まで遠くなる妊婦が出てくるため、負担を減らす補助事業や、緊急時の迅速な対応など、自治体による支援や対策も重要になります。
全国的に出産施設が減り、分べん空白市町村が広がっていることについて厚生労働省は「出産施設は減少しているが、各都道府県で、二次医療圏よりも広い、周産期に対応する医療圏を設定し、出産施設を確保しているところだ。現状では、自宅から医療機関までに比較的距離のあるケースも考えられる。地域の実情を踏まえて、妊婦の情報をあらかじめ地域の消防機関と情報共有するなど、対策を講じてもらうことが望ましい。今年度からこども家庭庁と連携して実施している出産前の宿泊費用の支援事業も活用してほしい」とコメントしています。
分べん数の拡大が見込めないなか、出産施設の経営改善・収益向上していくためには、現在の経営状況をリアルタイムに把握し、お産予約数から未来の予測等をして出産施設経営することが求められます。
NHK放送文化研究所「広がる“分べん空白市町村”」
(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241106/k10014629321000.html)を一部引用